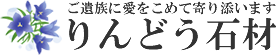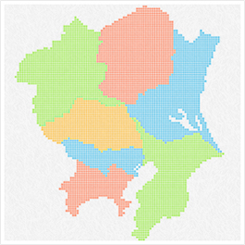天之御中主神
2023/04/02
こんにちは。
「天地初發之時 於高天原成神名 天之御中主神次高産巣日神 次神産巣日神 此三柱神者 並獨神成坐而隠身也・・・」この文は、古事記の冒頭にある言葉で「あめつちのはじめのとき、たかまがはらになりませるかみのみなは、あめのみなかぬしのかみ・・・」と読みます。
古事記は、「ふることふみ又は、ふることぶみ」と読み、和銅5年(712年)に稗田阿礼(ひえだのあ れ)の口述を太安万侶が編纂して、時の女帝元明天皇に献上されたことで成立する。
上中下の3巻から構成されています。
内容は天地開闢から推古天皇(日本初の女性天皇)の記事です。
本日は、冒頭の天之御中主神様についてのお話です。
天之御中主神様日本神話の天地開闢で最初に登場する神様です。
次高産巣日神 次神産巣日神(つぎたかむすびのかみ つぎかみむすびのかみ)と記され、この3柱 の神様は、造化三神と呼ばれています。
この中で天のみ仲主の神様は、至高の神として位置付けられています。
ちなみに・・・
・高産巣日神 天の生産・生成「創造」の神様。神産巣日神様と対となり、男女の「むすび」の男を象徴 します。
・神産巣日神 地の生産・生成の「創造」の神。高御産巣日神様と対となり、男女の「むすび」の女を象 徴します。
平安時代に成立した「延喜式神名帳」には天之御中主神様を祀る神社の名は記載されておらず、信仰の形跡は確認できおりません。
この神様が一般の信仰の対象になったのは、近世において天の中央の神ということから北極星の神格化である妙見菩薩と習合されるようになってからと考えられています。
主にこの神様を祭る神社には、妙見社系、水天宮系と、近代創建の大教院・教派神道系の3系統があります。
1.妙見社系の端緒は、道教における天の中央の至高神(天皇大帝)信仰にある。北極星・北斗7星信 仰、さらに仏教の妙見信仰(妙見菩薩・妙見さん)と習合され、熊本県の八代神社、千葉氏ゆかりの千葉神社、九戸氏ゆかりの九戸神社、埼玉県の秩父神社などは妙見信仰のつながりで天之御中主神を祀る妙見社です。
妙見社は千葉県では宗教法人登録をしているものだけでも50社以上もあ、全国の小祠は数知れません。
2.水天宮は、元々は天之御中主神様とは無関係だったが、幕末維新の前後に、新たに主祭神として追加されました。
3.明治初期に大教院の祭神とされ、東京大神宮や四柱神社などいくつかの神社が祭神に天之御中主神様を加え、また大教院の後継である神道大教を中心とする教派神道でも、多くの教団が天之御中主神をはじめとする全ての神々(神祇)を祭神としています。
その他、島根県出雲市の彌久賀神社などでも主祭神として祀られています。
出雲大社では別天津神の祭祀が古い時代から行われていて、現在も御客座五神として本殿に祀られています。
出雲大社が、古くは高層建築であったことは別天津神の祭儀と関係があるとする説があります。
また、天之御中主神様は、哲学的な神道思想において重要な地位を与えられることがあり、中世の伊勢神道では豊受大神を天之御中主神様と同一視し、これを始源神と位置づけています。
江戸時代の平田篤胤の復古神道では天之御中主神様は最高位の究極神とされている。
現在、天之御中主神様を祀る神社の多くは、妙見社や水天宮が明治期の神仏分離・廃仏毀釈運動の 際に天之御中主神を祭神とする神社となったものか、あるいは(復古神道の流れを引き継ぐ)大教院・教派神道系の神社です。
「天地初發之時 於高天原成神名 天之御中主神次高産巣日神 次神産巣日神 此三柱神者 並獨神成坐而隠身也・・・」この文は、古事記の冒頭にある言葉で「あめつちのはじめのとき、たかまがはらになりませるかみのみなは、あめのみなかぬしのかみ・・・」と読みます。
古事記は、「ふることふみ又は、ふることぶみ」と読み、和銅5年(712年)に稗田阿礼(ひえだのあ れ)の口述を太安万侶が編纂して、時の女帝元明天皇に献上されたことで成立する。
上中下の3巻から構成されています。
内容は天地開闢から推古天皇(日本初の女性天皇)の記事です。
本日は、冒頭の天之御中主神様についてのお話です。
天之御中主神様日本神話の天地開闢で最初に登場する神様です。
次高産巣日神 次神産巣日神(つぎたかむすびのかみ つぎかみむすびのかみ)と記され、この3柱 の神様は、造化三神と呼ばれています。
この中で天のみ仲主の神様は、至高の神として位置付けられています。
ちなみに・・・
・高産巣日神 天の生産・生成「創造」の神様。神産巣日神様と対となり、男女の「むすび」の男を象徴 します。
・神産巣日神 地の生産・生成の「創造」の神。高御産巣日神様と対となり、男女の「むすび」の女を象 徴します。
平安時代に成立した「延喜式神名帳」には天之御中主神様を祀る神社の名は記載されておらず、信仰の形跡は確認できおりません。
この神様が一般の信仰の対象になったのは、近世において天の中央の神ということから北極星の神格化である妙見菩薩と習合されるようになってからと考えられています。
主にこの神様を祭る神社には、妙見社系、水天宮系と、近代創建の大教院・教派神道系の3系統があります。
1.妙見社系の端緒は、道教における天の中央の至高神(天皇大帝)信仰にある。北極星・北斗7星信 仰、さらに仏教の妙見信仰(妙見菩薩・妙見さん)と習合され、熊本県の八代神社、千葉氏ゆかりの千葉神社、九戸氏ゆかりの九戸神社、埼玉県の秩父神社などは妙見信仰のつながりで天之御中主神を祀る妙見社です。
妙見社は千葉県では宗教法人登録をしているものだけでも50社以上もあ、全国の小祠は数知れません。
2.水天宮は、元々は天之御中主神様とは無関係だったが、幕末維新の前後に、新たに主祭神として追加されました。
3.明治初期に大教院の祭神とされ、東京大神宮や四柱神社などいくつかの神社が祭神に天之御中主神様を加え、また大教院の後継である神道大教を中心とする教派神道でも、多くの教団が天之御中主神をはじめとする全ての神々(神祇)を祭神としています。
その他、島根県出雲市の彌久賀神社などでも主祭神として祀られています。
出雲大社では別天津神の祭祀が古い時代から行われていて、現在も御客座五神として本殿に祀られています。
出雲大社が、古くは高層建築であったことは別天津神の祭儀と関係があるとする説があります。
また、天之御中主神様は、哲学的な神道思想において重要な地位を与えられることがあり、中世の伊勢神道では豊受大神を天之御中主神様と同一視し、これを始源神と位置づけています。
江戸時代の平田篤胤の復古神道では天之御中主神様は最高位の究極神とされている。
現在、天之御中主神様を祀る神社の多くは、妙見社や水天宮が明治期の神仏分離・廃仏毀釈運動の 際に天之御中主神を祭神とする神社となったものか、あるいは(復古神道の流れを引き継ぐ)大教院・教派神道系の神社です。