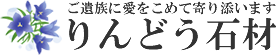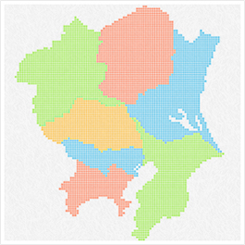安井春海と暦
2023/07/21
暦は、飛鳥時代の第33代推古天皇(日本初の女性天皇)12年(604)に百済(くだら)から暦を作成するための暦法や天文地理を学ぶために僧を招き、日本最初の暦が作られたと伝えられています。
「日本書紀」の第29代欽明天皇14年(553)6月に、百済から「暦博士」を招き、「暦本」を入手しようとした記事があります。これが、日本の記録の中で最初に現れた暦の記事であります。
暦は朝廷が制定し、大化の改新(645)で定められた律令制では、中務省(なかつかさしょう)に属する陰陽寮(おんみょうりょう)がその任務にあたっていました。
平安時代からは、暦は賀茂氏が、天文は陰陽師として名高い安倍清明(あべのせいめい 921-1005)を祖先とする安倍氏が専門家として受け継いでいくことになります。
当時の暦は、「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」別名で「太陰暦」、「陰暦」と呼ばれる暦でした。
暦の制定は、月の配列が変わることのない現在の太陽暦(たいようれき)とは違って非常に重要な意味をもち、朝廷の行事、農家の種まきの時期など、朝廷や後の江戸時代には幕府の管轄のもとにありました。
囲碁4家(徳川家から扶持を受けた4家の家元)のなかで、安井家の安井春海(別名渋川春海)1639年~1715年は、当時の宣明暦(862年に唐より伝来)を用いていたが、中国大陸とは、緯度が異なり、かなりの誤差が生じ、特に月食、日食の誤差が2日も遅れていたようです。
春海は、1670年32歳の頃より、日夜天体を観測し、その結果、元の授時暦(中国の暦別名大統暦)に戻すことを願いでたが、1975年に春海が授時暦に基づき、計算した日食の予想が外れ、申請は、却下されました。
春海は、失敗の原因を突き止めるべく、日夜研鑽の結果、太陽の運行の遅速に関わることに気づき、他の天文学者らの協力と自己の観測データなどを用いて、大和暦を作成。
その後、様々な紆余曲折があり、3度目の上奏により、朝廷の勅許を得て、貞享暦として、日本で初めての国産暦となりました。
明治に入り、太陽暦が制定されるまで、この歴は続きました。
また、安井春海は、囲碁の打ち手としても俊逸で、当時のお城碁(江戸時代将軍家の前で囲碁を打つ事)の上手7段として、活躍していました。
春海は、北極星が天文の太極であると称し、囲碁も1手も天元に着手していたようです。
もし、天元に打って負けたら、2度と天元には打たないと豪語していましたが、お城碁で本因坊道策(家元4家の1家)に負け、それ以後は、2度と天元には打たなかったようです。
「日本書紀」の第29代欽明天皇14年(553)6月に、百済から「暦博士」を招き、「暦本」を入手しようとした記事があります。これが、日本の記録の中で最初に現れた暦の記事であります。
暦は朝廷が制定し、大化の改新(645)で定められた律令制では、中務省(なかつかさしょう)に属する陰陽寮(おんみょうりょう)がその任務にあたっていました。
平安時代からは、暦は賀茂氏が、天文は陰陽師として名高い安倍清明(あべのせいめい 921-1005)を祖先とする安倍氏が専門家として受け継いでいくことになります。
当時の暦は、「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」別名で「太陰暦」、「陰暦」と呼ばれる暦でした。
暦の制定は、月の配列が変わることのない現在の太陽暦(たいようれき)とは違って非常に重要な意味をもち、朝廷の行事、農家の種まきの時期など、朝廷や後の江戸時代には幕府の管轄のもとにありました。
囲碁4家(徳川家から扶持を受けた4家の家元)のなかで、安井家の安井春海(別名渋川春海)1639年~1715年は、当時の宣明暦(862年に唐より伝来)を用いていたが、中国大陸とは、緯度が異なり、かなりの誤差が生じ、特に月食、日食の誤差が2日も遅れていたようです。
春海は、1670年32歳の頃より、日夜天体を観測し、その結果、元の授時暦(中国の暦別名大統暦)に戻すことを願いでたが、1975年に春海が授時暦に基づき、計算した日食の予想が外れ、申請は、却下されました。
春海は、失敗の原因を突き止めるべく、日夜研鑽の結果、太陽の運行の遅速に関わることに気づき、他の天文学者らの協力と自己の観測データなどを用いて、大和暦を作成。
その後、様々な紆余曲折があり、3度目の上奏により、朝廷の勅許を得て、貞享暦として、日本で初めての国産暦となりました。
明治に入り、太陽暦が制定されるまで、この歴は続きました。
また、安井春海は、囲碁の打ち手としても俊逸で、当時のお城碁(江戸時代将軍家の前で囲碁を打つ事)の上手7段として、活躍していました。
春海は、北極星が天文の太極であると称し、囲碁も1手も天元に着手していたようです。
もし、天元に打って負けたら、2度と天元には打たないと豪語していましたが、お城碁で本因坊道策(家元4家の1家)に負け、それ以後は、2度と天元には打たなかったようです。