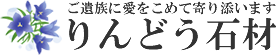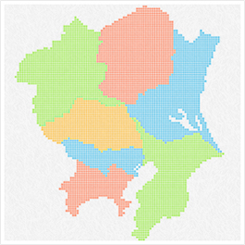日本での仏壇の始まり・・・。。
2019/03/13
日本での仏壇の始まりは・・・
西暦685年第40代天武天皇の「諸国の家毎に仏舎を造り仏像を安置し、礼拝供養するように」との詔勅( みことのり)があり、広まったとあります。
これが、日本における仏壇の始まりとされていますが、「諸国の家毎に」とは、庶民の家を指す言葉ではなく、貴族や諸国の官庁などに限ら有れたそうです。
この勅がだされた3月27日は、今日では「仏壇の日」とされています。
仏壇が、庶民の家で広く全国的に奉られるようになったのは、江戸時代に入ってからです。
江戸幕府がキリシタン禁制と民の統制を目的として、寺受け制度を設け、お寺が民の戸籍を管理し、民衆は各家毎にそれぞれの寺院に檀家としてその寺院を菩提寺とすることを義務付け、家毎に仏壇を設け、朝・夕礼拝して、先祖の命日は僧侶を招いて供養するという習慣が定着したようです。
西暦685年第40代天武天皇の「諸国の家毎に仏舎を造り仏像を安置し、礼拝供養するように」との詔勅( みことのり)があり、広まったとあります。
これが、日本における仏壇の始まりとされていますが、「諸国の家毎に」とは、庶民の家を指す言葉ではなく、貴族や諸国の官庁などに限ら有れたそうです。
この勅がだされた3月27日は、今日では「仏壇の日」とされています。
仏壇が、庶民の家で広く全国的に奉られるようになったのは、江戸時代に入ってからです。
江戸幕府がキリシタン禁制と民の統制を目的として、寺受け制度を設け、お寺が民の戸籍を管理し、民衆は各家毎にそれぞれの寺院に檀家としてその寺院を菩提寺とすることを義務付け、家毎に仏壇を設け、朝・夕礼拝して、先祖の命日は僧侶を招いて供養するという習慣が定着したようです。