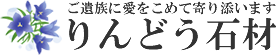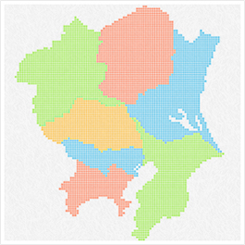火葬のお話し
2019/03/17
火葬のお話し
前回、第40代天武天皇の事蹟(日本の位牌の始まり)を書きましたが、この天皇の後を継いだのが奥様である第41代持統天皇です。
この方は第38代天智天皇の娘にあたり、百人一首では、天智天皇の御製である「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ」を第1番に2番目に「春ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすちょう 天の香具山」
という御製が挙げらています。
ここまでは、教科書やさまざまな書物によって流布されていますが、本来、教科書に赤線付きで載るべき天皇なのです。
実は、天皇で初めて火葬されたのが、持統天皇なのです。
続日本紀によると、702年に持統天皇が火葬されたとの記述が残っています。
これよりさかのぼる2年前の700年に日本で最初に火葬されたのは、僧:道昭です。
道昭は、学問僧として、遣唐使として唐に渡り、玄奘三蔵(西遊記で有名)の弟子になりました。
仏教の祖である釈迦は、「すべては『空』であるから自分の死後は火葬にせよ」
という遺言によって火葬されました。
道昭はその釈迦に倣って火葬を望んだのです。
道昭は、天武天皇からの勅命で、往生院を建立するなど、天皇から最も信頼されていた我が国一番の僧でした。
持統天皇はその道昭にならい、火葬を望んだのです。
前回、第40代天武天皇の事蹟(日本の位牌の始まり)を書きましたが、この天皇の後を継いだのが奥様である第41代持統天皇です。
この方は第38代天智天皇の娘にあたり、百人一首では、天智天皇の御製である「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ」を第1番に2番目に「春ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすちょう 天の香具山」
という御製が挙げらています。
ここまでは、教科書やさまざまな書物によって流布されていますが、本来、教科書に赤線付きで載るべき天皇なのです。
実は、天皇で初めて火葬されたのが、持統天皇なのです。
続日本紀によると、702年に持統天皇が火葬されたとの記述が残っています。
これよりさかのぼる2年前の700年に日本で最初に火葬されたのは、僧:道昭です。
道昭は、学問僧として、遣唐使として唐に渡り、玄奘三蔵(西遊記で有名)の弟子になりました。
仏教の祖である釈迦は、「すべては『空』であるから自分の死後は火葬にせよ」
という遺言によって火葬されました。
道昭はその釈迦に倣って火葬を望んだのです。
道昭は、天武天皇からの勅命で、往生院を建立するなど、天皇から最も信頼されていた我が国一番の僧でした。
持統天皇はその道昭にならい、火葬を望んだのです。